チェックネクタイ徹底解説

レジメンタルストライプ、小紋、ペイズリー、水玉などネクタイの柄にはたくさんの種類がありますが皆さんはチェック柄のネクタイはお持ちですか。
チェック柄といっても様々な種類のチェックがあり、縞の幅や縞のバランスなど、たくさんのバリエーションがあります。チェック柄と聞くと、思い浮かぶのはブランドの伝統的なチェック柄を想像する人が多いと思います。Burberry(バーバリー)、DAKS(ダックス)、MACKINTOSH LONDON(マッキントッシュ ロンドン)、Aquascutum(アクアスキュータム)、百貨店では伊勢丹の紙袋のチェック柄など、皆さんがご存知のブランドやお店もたくさんあるのではないでしょうか。チェック柄は一目見て、どこの商品であるかわかってしまうほどインパクトや個性があり、ブランドの象徴にもなるほどの柄です。チェック柄には、伝統と歴史があるものが非常に多くあります。それぞれのチェック柄の歴史を知ることにより、チェックネクタイをしめる際に今まで以上に愛着をもってしめていただけるような、チェックネクタイの知られざる秘密について話をしていきます。
チェックネクタイの意味、語源
チェック柄の意味や、語源について知っていますか。
秋、冬などの寒い季節になると、トラッドなチェックを身につけたくなる方も多いと思います。何気なく手にとり、しめているチェックのネクタイですが、チェックにはたくさんの種類があり、皆さんが知らないとっても興味深い歴史、伝統があります。その原点を知ることにより、ネクタイのチェック柄が今までと違って見えてくるのではないでしょうか。諸説、色々な言い伝えがありますが、一つの言い伝えとしては、紀元前1200頃にミイラが格子柄の生地を着用している状態で発見されていたそうです。
日本人は、チェックよりも格子柄の方を身近に感じる方が多いかもしれませんが、基本的に、格子柄模様を総称してチェックと呼ぶため、格子とチェックは同じ意味であると考えていいと思います。ちなみに英語では、「check」よりも「plaid」や「checkered」と表現することのほうが多いそうです。チェックの意味としては、縦の縞と横の縞が重なり一定の間隔で重なっている模様の相性を指します。チェックはとても歴史のある柄です。
知っておきたいチェックネクタイの種類、歴史
チェックネクタイは特に秋冬の商品に多く、色々な縞模様の色鮮やかなチェック柄が街を彩る季節でもあります。蝶ネクタイとしても人気があり、とても華やかで、見る人の気持ちを優しい気持ちにさせてくれるのもチェックの特徴のひとつです。メンズのファッションの中でも少し可愛さをプラスしてくれるポイントとしても重要な柄です。チェック柄にはたくさんの種類がありますが、その一つ一つのチェックには意味があり歴史がありますので、それぞれ紐解いて解説していきます。
ウィンドーペンネクタイ
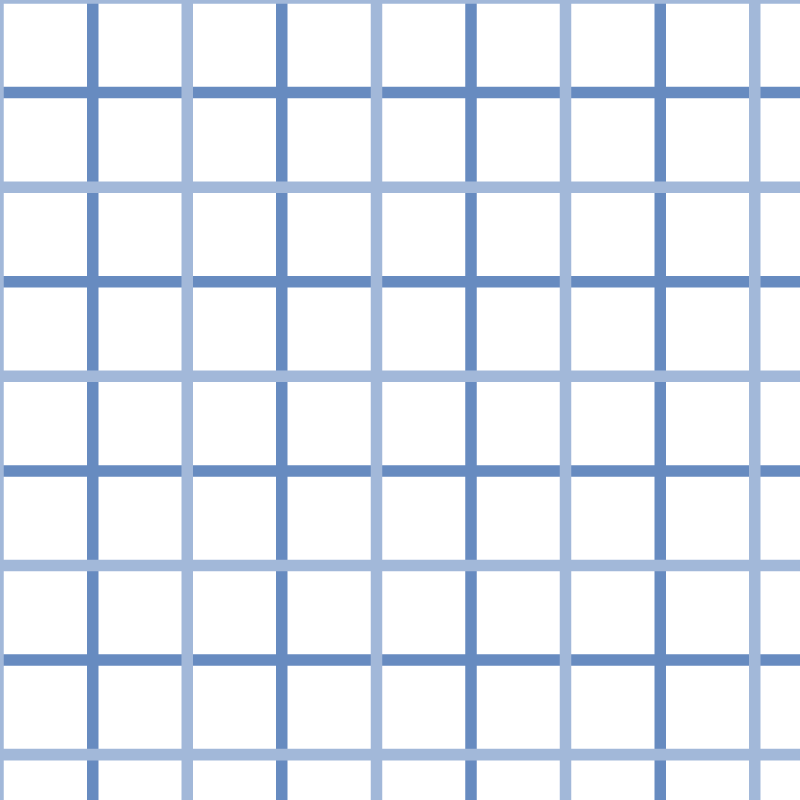
代表的なチェック柄の一つであるウィンドーペン(ウィンドウペン)。イギリスを代表する伝統的なチェックです。窓枠の格子(イギリスの田舎にあるような家)のような四角形をシンプルで等間隔に描いているチェック柄。生地の色とラインの横縞と縦縞の合わせて2色を使って構成されているチェックです。数あるチェック柄の中でも非常にシンプルなチェックとして知られています。チェック柄のため、程よいカジュアル感もありながら、歴史があり伝統のあるクラシックな柄であるため、上品な印象も与えることができます。
シンプルなチェック柄であるため色の組み合わせにより、イメージがかなり変わってしまうため、その部分には注意が必要です。地色とチェックのラインの色の差が大きいと、チェックの柄がより目立つためインパクトのある印象を与えます。逆に、チェックと地の色が近いと、チェックの柄が目立ちにくくなるので、落ち着いたシックな印象を与えることができます。シンプルな柄のため、色の影響を受けやすく、着用する際は使用用途や着用シーンを考慮した上で選ぶことをオススメします。
グレンチェックネクタイ
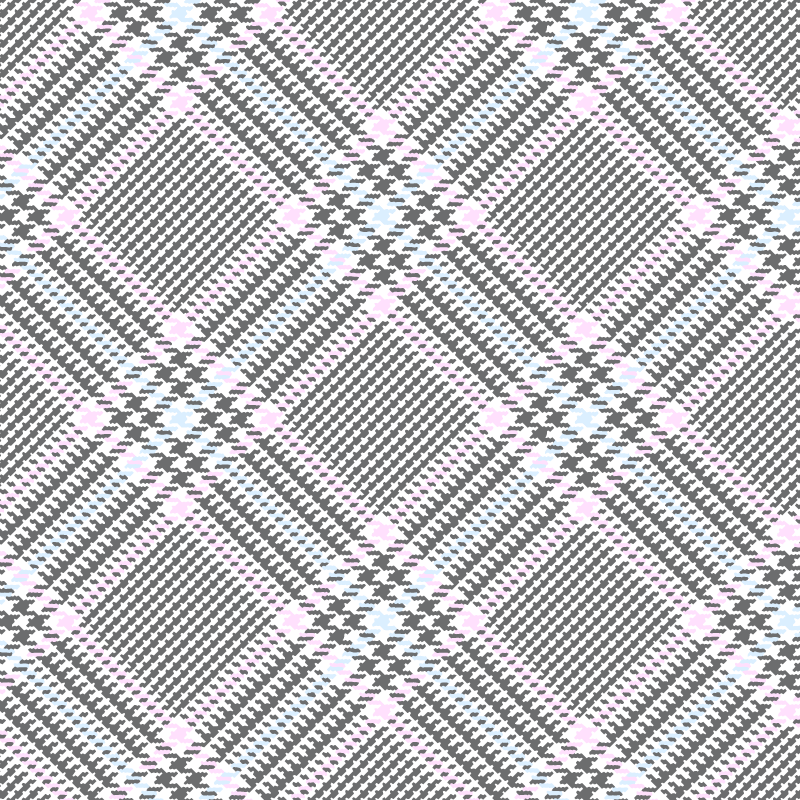
綾織り、もしくは斜子織りで織られ千鳥格子(ハウンドトゥース)と、ヘアラインストライプを組み合わせた大きな格子柄を形成しているチェック柄。
スコットランドの渓谷で織られていたことが、グレンチェックの名前の由来とされています(グレンとは渓谷とか谷間の意味)。正式名称は「グレナカートチェック」現在では「グレンチェック」と呼ばれています。ネクタイ、スーツ、ジャケット、スカート、ワンピースなど、性別にかかわらず幅広い商品に使われているチェック柄になります。柄に立体感があるため、重厚感を感じ、より上品なイメージを与えることができます。
ハウンドトゥースネクタイ
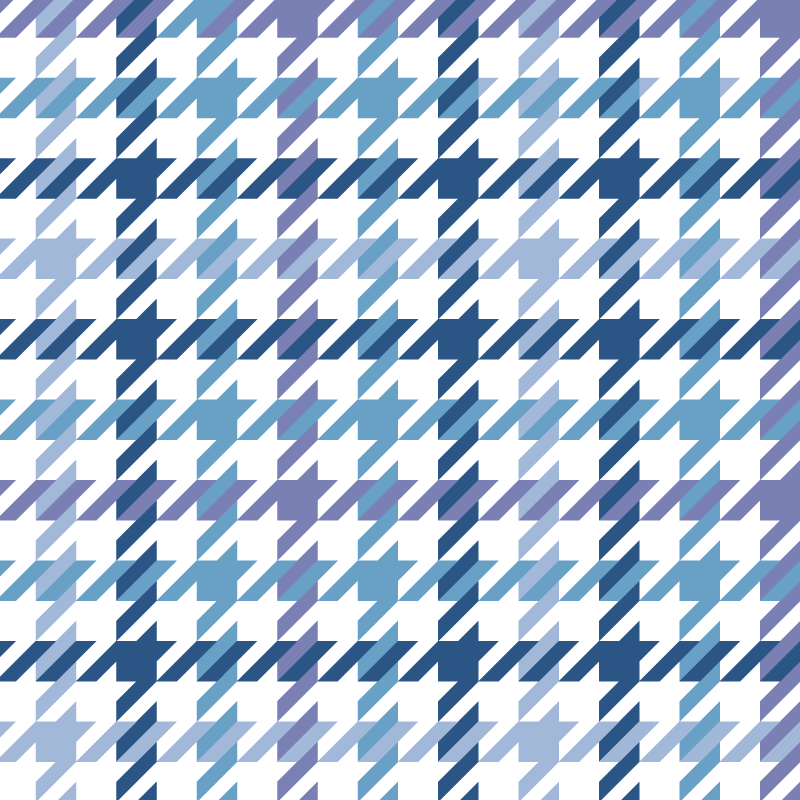
ハウンドトゥースを英語で書くと、「hound’s tooth」。「hound(ハウンド)」は猟犬、「 tooth(トゥース)」は歯の意味をさします。チェックを構成している柄が、犬の牙のように見えることが名前の由来とされています。犬の牙のような特徴的な柄が、連続して規則正しく並んでいるのが特徴的なチェックです。日本では空を飛ぶ鳥のように見えることから「千鳥格子」と呼ばれています。日本人には、千鳥格子の方が馴染みがあるかもしれません。ハウンドトゥースの起源はスコットランドのローランド地方であると言われています。
ブラック×ホワイト、ネイビー×ホワイトなど、ツートーンな配色が多く、色のコントラストが比較的強いものが多いのも、この柄の特徴です。色のコントラストが強いことから、コーディネートのアクセントにも非常に適している柄です。柄の大きさが大きくなると、よりチェックのインパクトを感じさせることができます。ただ、その反面、全体のアクセントにはなりやすい柄ですが、柄が大きすぎるとインパクトが強くですぎてしまう恐れがあるため、柄の大きさには注意が必要です。小〜中柄ですと、コーディネートの中でも程よく印象的なアクセントになり、上品で大人らしさを表現することができます。先程、紹介しましたグレンチェックは、ハウンドトゥースの千鳥格子にヘアラインストライプのチェックを組み合わせた柄になります。
タータンチェックネクタイ
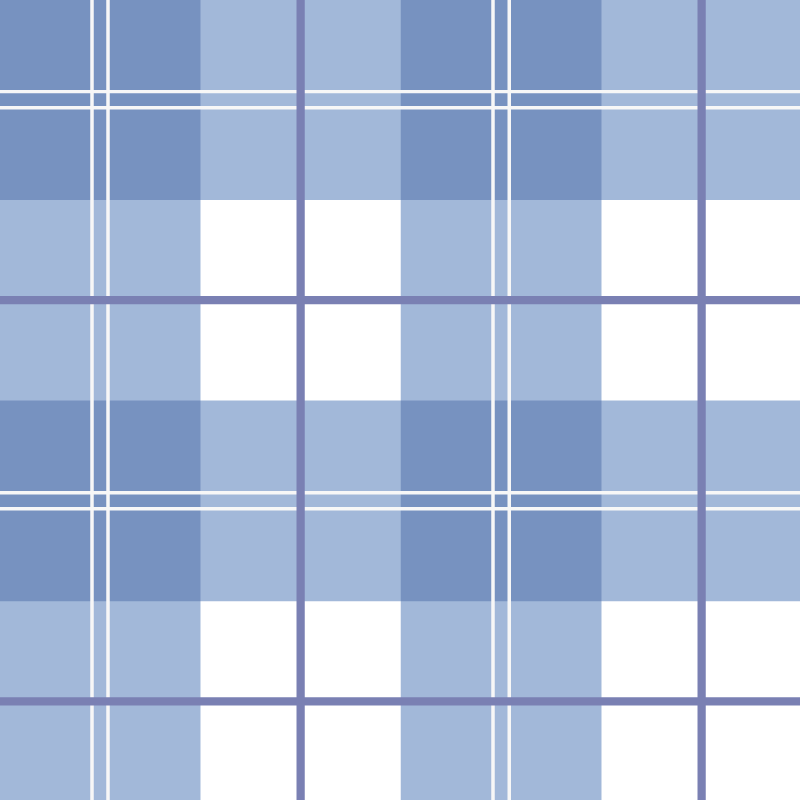
チェック柄の代表的な柄といえば「タータンチェック」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。チェック柄の一つでは終わらない、大人気の柄であるタータンチェックの魅力、そして奥深い歴史を紹介していきます。
タータンの定義としては、多色の色をウールの糸を使い、綾織にした格子柄の織物の総称を指します。日本では、タータンチェックと呼ばれていますが、正確には「タータン」「タータン・プラッド」と呼ぶことが一般的です。タータンの生地は、スコットランドのハイランド地方で昔から織られてきました。16世紀〜17世紀頃にハイランド地方の衣装として定着したものと考えられています。氏族ごとにタータンがあり、日本の家紋と同じような位置付けのものとして考えられてました。また、戦の際に味方がわかるように使われていた歴史もあるそうです。
ちなみにタータンの柄に関してはスコットランド・タータン登記所が保護、保存などを目的としてデザインを登録管理しています。ここに申請することにより、初めてタータンとして認められ、正式にタータンと呼ぶことができます。近年は、日本でも例があるので、それについてもお話しします。
タータンチェックの地方の取り組み
北海道の日本海側にある町、余市町。古くは江戸時代から明治、大正時代にかけて、ニシンの大群が北海道に押し寄せ、ニシン漁で非常に栄えた町。北海道を代表する民謡である「ソーラン節」は、ニシン漁で雇われたヤン衆たちに歌われてきた仕事歌です。余市町は、ソーラン節発祥の地として知られている町になります。余市町が全国に知れ渡ったきっかけは、2014年後期のNHKドラマ「マッサン」で、竹鶴政孝氏(ニッカウヰスキー(株)創業者)とリタ夫人のウイスキー造りにかける情熱と愛の物語でした。マッサンとリタの物語を後世に残すために、また、余市町とイースト・ダンバートンシャイア市(現在のイースト・ダンバートンシャイア市、姉妹都市、英国・スコットランドの南西部)との関係を広く周知するため、スコットランドの伝統的な装飾柄のタータンチェックにその橋渡し役を求めました。そのような背景があり、2018年「Yoichiタータン」が誕生しました。「Yoichiタータン」で、使われているカラーは、余市の沖の海の色である「青」、「波」と「雲」を表現した白、余市のシンボルである「リンゴ」や「サクランボ」の赤を表現しています。町独自のタータンチェックは、町の魅力、ブランドイメージなどの発信にも大活躍中です。JR余市駅の周辺では、「Yoichiタータン」の旗も見られ、町を上げて取り組まれている事業です。その中の新作商品として、弊社が携わっています商品があります。特注の経糸を使用している「Yoichiタータン」のネクタイ。弊社の八王子工場で織り上げた、こだわりの日本製。コーディネートのワンポイントのアクセントとしても可愛いネクタイです。レディースファッションとしても可愛く、男女問わず楽しめる商品であると思います。制服にあわせるのも素敵ではないでしょうか。余市町観光協会のHP で商品は確認することができます。
マドラスチェックネクタイ
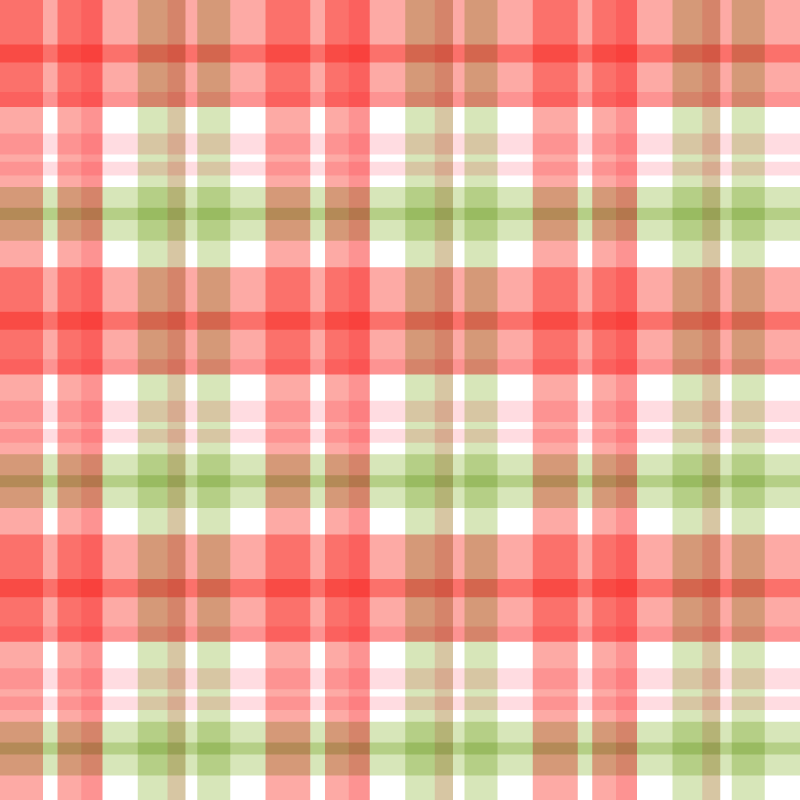
ネクタイよりも、コットンを使ったネルシャツなどのカジュアルなシャツなどで見ることの多い柄であるマドラスチェック柄。多色使いのものが多いため、よりカジュアルな商品にコットンの素材でよく使われるイメージの強いチェックです。
タータンチェックは綾織の織組織のものでしたが、マドラスチェックは、薄地の平織りで綿素材を使用したものが多いと思います。マドラスチェックの発祥の地として知られている町は、インド南東部のベンガル湾に面する都市マドラスです(現在のチェンナイ)。マドラスは17世紀ごろ、イギリス東インド会社の貿易拠点として商業・文化の中心地として発展しました。
1920年頃、Brooks Brothers(ブルックスブラザーズ、アメリカ)にて、初めてファッションとして採用。その後、爆発的に人気が出たことにより、世界、そして日本でも知られるようになった、カラーが特徴的なチェック柄です。アメカジ(アメリカンカジュアル)のチェックシャツとしても人気の柄です。夏物として、リネンを使ったものなど清涼感のあるものもありますので、商品を探す際には参考にして下さい。
ギンガムチェックネクタイ
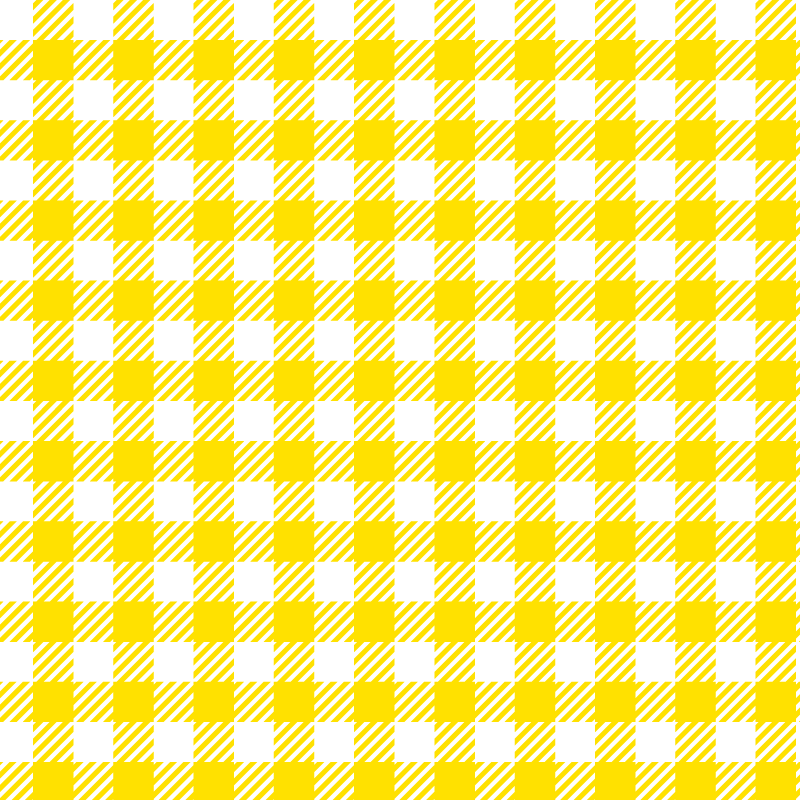
日本でも馴染みのあるチェックで、好きな方も非常に多い柄であると思います。可愛いチェックといえばこのチェックをあげる方が多いほど、可愛いチェックとしても認知されているチェック柄。男性の場合は、ボタンダウンのギンガムチェックのシャツとジャケットを合わせたり、ビジネスでスーツと合わせて着られる方も多いかと思います。女性の場合は、ワンピースやスカートなどでも見ることが多く、ギンガムチェックの生地の面積が大きくなると、より爽やかに感じます。AKB48の曲でも「ギンガムチェック」という曲があるくらい馴染みのあるチェックの一つです。
ギンガムチェックは平織綿布の一種です。たてと横、地の縞と均一の幅にし正方形の柄目にしたチェックで単純な2色使いのものが多いことも特徴の一つ。イメージとしては、ネイビー×白、ブルー×白の印象をもっている人が多いかと思います。ヨーロッパでは「ヴィシーチェック」と呼ばれることもあるそうです。
ギンガムチェックの由来としては、諸説色々とありますが、マレー語で縞模様という意味の「Genggnag」に由来しており、語源となっているという説があります。
マルチチェックネクタイ

多色使いの格子柄や、タテの縞、横の縞に太細など強弱があるものを、マルチチェック(マルチカラーチェック)と呼んでいます。
チェック柄の中でもマルチチェック柄は非常に多く、ネクタイの場合もマルチカラーチェックの柄が特に多いように思います。ビジネスの際のワイシャツにも一番合わせやすいチェック柄であると思います。ネクタイではレギュラー(定番的な)なチェック柄です。色々なチェックのアレンジが可能なので、チェックの柄の種類にも幅があり、多種多様なものがあります。チェックの大きさ、線の太さ、チェックのバランスなど、用途や、シーンなどに合わせてしめていただきたいチェック柄です。就職祝いや、父の日のプレゼントとしてもオススメのチェックです。
チェックネクタイのカラーを選ぶ際のポイント
つづいて、チェックネクタイのカラーを選ぶ際のポイントです。
チェック柄とは、縦の縞と横の縞が重なり一定の間隔で重なっている模様のことをいいます。チェックは全体的にしつこくなりがちな柄のため、他の柄と比べても、色の組み合わせ、色の使い方をより気にする必要がある柄です。
ネクタイのカラーについては、ご自身の立場やシーンに合わせてネクタイのカラーを変えることもおすすめです。たとえば、商談の際には「ネイビー」や「ブルー」のような誠実なイメージを持たせるカラーを選び、プレゼンテーションの際には情熱をアピールできる「赤」や「ワイン」を選ぶなどの色の使い分けは、非常に大切なことになります。ここでは、チェックネクタイのそれぞれの色があたえるイメージを紹介します。
ネイビー、ブルー系のネクタイがあたえるイメージ
ネイビーやブルー系のネクタイは、誠実で知的、聡明な印象をあたえるとされています。これらのカラーは、ビジネスシーンにおいて定番中の定番、一番使いやすいネクタイと言われており、好印象をあたえるために何本か持っておくと便利です。
ワイン、赤系のネクタイがあたえるイメージ
赤系のネクタイといえば、アメリカの元大統領をイメージする方も多いかと思いますが、自分自身の熱意を伝えたい立場の方が、好んでしめられているのも印象的です。営業系の業種など、大事なプレゼンの際など、よりエネルギッシュで活動的な印象を与えたい方には特にオススメです。
ゴールド、イエローなどのイエロー系のネクタイがあたえるイメージ
黄色には相手の警戒感を緩和させる力があるとされています。より協調性を重視される場面や、就職活動の際の企業の都政に合う企業であれば、とても効果的なカラーであると思います。ただ、イエローの発色に関しては、シーンによって濃度、発色など派手になりすぎない注意が必要です。
グリーン、エメラルドグリーン、カーキなどのグリーン系のネクタイがあたえるイメージ
グリーンは自然を思わせる色で、そのナチュラルな印象は穏やかさを求める方に最適です。近年では、当サイトでもグリーンのネクタイは人気色の一つとなっています。まだグリーンのアイテムをお持ちでない方には、ぜひ一度試してみていただきたい色です。また、紺やブルー、グレーなどとの相性が良いため、スーツやシャツにも簡単に合わせることができます。
ブラウン、ベージュ系のネクタイがあたえるイメージ
落ち着いた、大人っぽい印象をあたえる色になります。ネクタイの定番カラーの一つで、持っていると非常に使い勝手がいいカラーでもあります。ネイビー、ブルー、グレーなどとも相性がよく、スーツ、シャツにも非常に合わせやすいため、コーディネートにもとても使いやすい色です。
グレー、シルバーのネクタイがあたえるイメージ
落ち着いた印象を相手に与えることができるカラーです。他の色とも相性が非常にいいため、コーディネートの幅が広くあわせやすいのも魅力の一つとされています。コーディネートが苦手な方などは、一本あるととても使いやすいカラーです。営業や、商談の際にはもちろんのこと、パーティーシーンにおいても活躍できるカラーです。
オレンジ系のネクタイがあたえるイメージ
明るいカラーにポジティブな印象を与えることのできる、元気をもらえるような色。少し悩みがある時や、落ち込んでいる時など、自分に元気を与える意味も込めて、着用してみるのもいいと思います。ビジネスで使う場合は、あまりオレンジが鮮やかになりすぎない、深めのオレンジ色を着用されるのがいいと思います。
ライトブルーのネクタイがあたえるイメージ
清潔感、爽快感などフレッシュな印象をあたえる効果があります。ビジネス、就職活動など色々なシーンで活躍する一本です。海や、空をイメージする色でもありますので、夏のクールビズシーズンにもぴったりの色です。またライトブルーには、人の視線を集める効果も期待できます。黒、ネイビー、グレーなどスーツとのコーディネートにもあわせやすい色なので、是非挑戦してみてください。
その他のネクタイの色の印象について
最後に、その他の色、黒、白、紫のネクタイについても少し触れておきます。それぞれ、組み合わせるのが難しい印象をお持ちかもしれませんが、以下のような印象を与えますので、ここぞというシーンでぜひ着用してみてくださいね。
シーン別チェックネクタイの選び方
チェックネクタイを選ぶ際に、「このシチュエーションに、このドットネクタイはどうかな?」と、悩んだことのある方も多いと思います。そんなチェックネクタイを、シーン別にして、まとめてみました。悩むことが多そうな結婚式、就職、転職活動などについても解説していきます。
結婚式のチェックネクタイの選び方
まず、結婚式の服装のルールとして、これだけは必ず抑えておきたいのは、「結婚式の主役は新郎新婦」ということです。参列者はあくまで主役を立てるのが大人としてのマナーです。ネクタイに関しても派手になりすぎないことがとても重要です。ゲストとして結婚式に出席する際に、どんなネクタイをしめたら良いか悩んだ経験がある方は多くいると思います。今回は、その中でもチェックネクタイの選び方についてフォーカスしました
結婚式におすすめのチェック柄ネクタイ
まず、チェック柄は、結婚式などのパーティーシーンなどにもあわせやすい柄であると思います。ただ、チェック柄の柄によってはカジュアルになりすぎてしまう恐れもあるため、その部分は注意が必要です。オススメのチェックとしては、ウィンドーペン、グレンチェック、ハウンドトゥース、マルチチェックなどがオススメです。
織物(ジャガード)の程よい凹凸感、サテンのような光沢感のある織組織のものは、高級感やリッチ感を感じることができます。シルク(絹)の糸を生かした繊細な表情を感じる商品や、光の角度により感じることのできる陰影は、ネクタイならではの織物(ジャガード)の魅力であると思います。結婚式、卒業式などのおめでたい席にはぴったりであると思いますので、意識して選んでほしいです。チェックのネクタイを選ぶ際には、できるだけフォーマルスーツはシンプルな柄のものがスタイリングもしやすいと思います。チェックのネクタイにインパクトがあるため、スーツはあまり主張しすぎないシンプルなものが良いと思います。ネクタイピンをチェックネクタイにあわせる際にも同様に、よりシンプルなものが良いです。あわせてポケットチーフ、カフスなどの小物もスタイリングの一つとして入れると、さりげないオシャレ感が増してさらに華やかになると思います。ファッション小物にも注目してスタイリングをしてみると、よりチェックネクタイの存在価値をあげることができると思います。
結婚式におすすめのチェックネクタイカラー
ネクタイの結婚式の定番カラーといえば「白」。結婚式に参加すると、ネクタイは「白」を着用されている方が圧倒的に多いかと思います。定番のカラーは「白」です。間違われる方がたまにいますが、ネクタイの色に関しては、結婚式は「白」、お葬式は「黒」になりますので、お間違えのないようにして下さい。近年の結婚式にしめるネクタイのカラーで人気のものは「シルバー」です。白よりも少しシックに見えるため、20代〜30代を中心に今、非常に増えているカラーです。弊社のネクタイ販売サイト「SEIWA ONLINE」でもフォーマルネクタイとしてのシルバーのカラーは非常に人気のあるカラーです。是非、結婚式で一度トライして欲しいと思います。近年はフォーマルネクタイも多様化しており、カラーフォーマルと言われている淡いカラーのネクタイも少しずつ増えてきています。ピンク、ライトブルー、シャンパンゴールドなどのカラーもオススメです。結婚式なので、可愛く、華やかに見える、淡いピンクや、シャンパンゴールドといったカラーを着用されるのも、特別感があり良いかと思います.。ネクタイのタイ幅(ネクタイの一番太い部分の長さ)が細いナロータイも結婚式には人気のネクタイです。通常のネクタイより細いので、よりスタイリッシュな印象をあたえることもできます。是非、ナロータイもチェックしてみて下さい。
就職、転職活動などリクルート用のチェックネクタイの選び方
就職活動、転職活動において避けることができないものが採用面接。近年は新型コロナウィルスの影響などもあり、リモートでの面接が非常に増えてきました。ただ、リモートの面接に関しても身だしなみは非常に重要です。体の中心にあると言われているネクタイは、目に入ってくる情報として、印象を決める部分としても非常に重要な部分になります。ネクタイで、少しでもご自身の印象をよくできるのであれば、絶対に試してみたいですよね。そんな、就職、転職活動にぴったりなチェックネクタイを紹介します。
就職、転職活動にオススメのチェックネクタイ柄
就職、転職活動にもチェック柄は非常にオススメです。
チェック柄のネクタイは、相手に親近感を与えやすい柄であると言われています。あわせて明るい印象も感じさせることができるため、初対面の方と会う場合などに着用すると、より効果を発揮できると思います。就活などの面接にはもってこいの柄です。チェックは、おしゃれを感じることのできる柄でもあるので、よりおしゃれな雰囲気を出したい面接の場合にもオススメの柄です。チェックの色数をたくさん使っているものは、カジュアルな印象を与えてしまう可能性があるので、色数のまとまったものや、織り組織に凹凸感があるネクタイを選ぶことで、就活の際の面接にも着用しやすくなります。ネクタイは織組織などによっても高級感も出すことができるため、落ち着いた大人っぽい印象を与えることも可能です。チェックは若々しい印象も与えることができるためどの年代でも、長く楽しめる柄でもあると思います。
就職、転職活動にオススメのネクタイカラー
ネイビーやブルーのネクタイは定番中の定番カラーで、「誠実」「知的」「聡明」などの好印象をあたえるため、必ず一本は持っておきたいカラーです。一方、ワインや赤系のカラーは「積極性」「エネルギッシュ」「情熱的」な印象を与え、より活動的な部分をアピールしたい場合に着用すると良いでしょう。また、イエロー系のカラーは「ポジティブ」「協調性」「親しみやすさ」「社交的」な印象をあたえ、相手の警戒感を緩和させる力があり、協調性を重視される企業には特に効果的です。
チェックネクタイをしめるときの注意点
チェックネクタイをしめる際の注意点が3点あります。チェックの大きさ、色のコントラスト、チェック全体の色数の3つです。
- 着用するシーンによっては、あまり色数の使っていないチェックを選ぶ。色数が多いと派手になってしまい胸元にアクセントがつきすぎる(個性的になりすぎて しまう)可能性があるため。
- チェックの大きさには気をつける。チェック柄は大きければ大きいほどカジュアルに見えてしまう傾向があるため、着用するシーンなどに考慮した柄の選択を心がける。
- ビジネスなどで着用の場合は、色のコントラストがつきすぎていないものを選ぶ。色のコントラストが強いもの(ブラック×ホワイト、ネイビー×ホワイトなど)は、カジュアル感が強いので、着用シーンによってはできるだけ避けるようにする・逆に、よりカジュアルにジャケットスタイルのコーディネートをしたい方は色のコント ラスト、チェックの大きさにはそこまで気を使う必要はないかと思います。
最後に
ネクタイの定番の柄の一つであるチェック柄。チェック柄には深い歴史があり、現在でもその歴史はしっかりと受け継がれています。普段何気なく着用しているチェックネクタイも、チェックの大きさや色、チェックの縞の太さ、バランスなどによって、異なる印象を相手にあたえることができます。物事を深く知る意味を感じ、これからのネクタイを着用する機会の際に思い出してもらえると、とても嬉しいです。
1935年創業のネクタイ・ネックウェアのファクトリーメーカー 、成和株式会社です。東京(八王子)に自社工場を持ち、匠の技術を活かした高品質のネクタイを軸に展開しています。 創業以来、自社工場で製織される匠の技術を持った高品質のネクタイを一人でも多くのお客様に直接手に取っていただきたい思いから開設したサイトはこちらです。皆様の思い出に残るような、お気に入りのネクタイが見つかればとても嬉しいです。






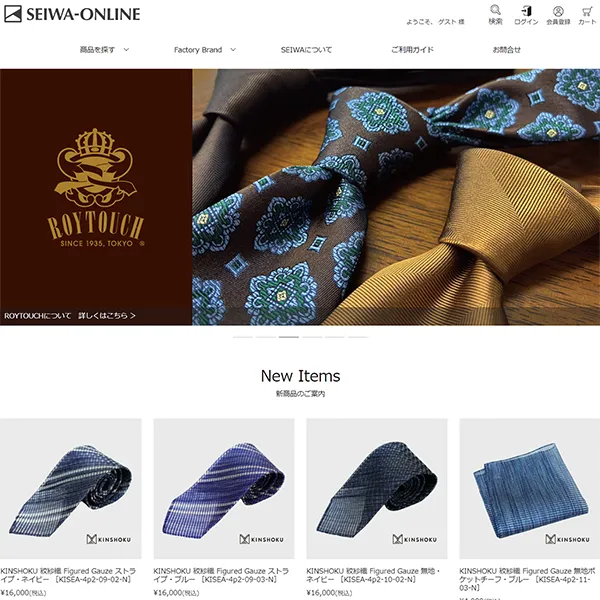 製造工場が運営するネクタイ通販サイト
製造工場が運営するネクタイ通販サイト